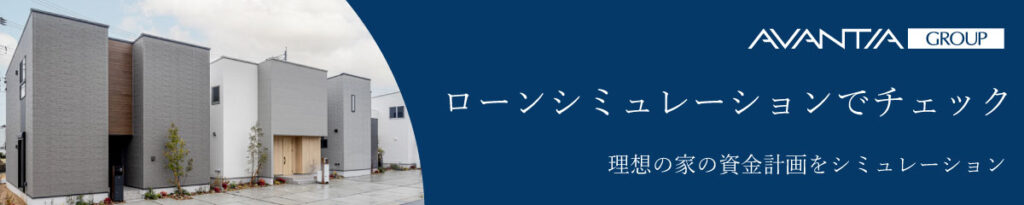住宅ローン控除、2025年も使える?変わる?
住宅購入を検討する際、資金計画とあわせて必ず押さえておきたいのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
この制度は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税や住民税が一定額控除される仕組みで、家計にとっては非常に心強い“節税メリット”がある制度として、多くの方に活用されています。
2025年もこの控除制度は継続されるものの、制度の内容には複数の変更が加えられており、従来のイメージのままで活用しようとすると「控除を受けられなかった」「控除額が思ったより少なかった」といった事態に陥ることもあります。
本記事では、2025年度版の住宅ローン控除制度について、最新の改正ポイントを中心に、知っておくべき注意点や活用のための実践的なアドバイスを詳しく解説します。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額が、所得税・住民税から控除される制度です。
基本ルール(2025年版)とは?
- 控除額:年末残高の0.7%
- 控除期間:最大13年間(住宅の性能によって異なる)
- 控除対象上限:3,000万円〜4,500万円
- 控除対象:新築住宅、一定条件を満たした既存住宅(中古)
つまり、住宅ローン残高が多いほど、初年度〜数年間の控除額が大きくなります。たとえば年末時点での残高が2,900万円なら、控除額は約20万円(0.7%)となり、これが数年続くと累計で100万円以上の節税効果になることもあります。
2025年版:控除制度の主な変更点まとめ
2025年からの制度改正によって、特に大きな影響があるのが以下の3点です。
ポイント1:「省エネ性能」が控除の鍵に
新制度では、省エネ性能の高い住宅がより優遇されるようになり、逆に一定の基準を満たしていない住宅は控除対象外となりました。
| 住宅の種類 | 控除期間 | 年末残高の上限 | 控除率 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅/ZEH等 | 13年間 | 4,500万円 | 0.7% |
| 一般の省エネ基準住宅 | 10年間 | 3,000万円 | 0.7% |
| 基準未満の住宅 | ― | 対象外 | ― |
※省エネ基準=断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4以上
つまり、建物性能が基準を満たしていなければ、住宅ローン控除を一切受けられない可能性もあるため、購入前から設計・仕様確認が必須です。
ポイント2:中古住宅にも適用。ただし条件あり
新築だけでなく、中古住宅でも住宅ローン控除を受けることは可能です。ただし、下記の条件を満たす必要があります。
- 築年数:木造等は20年以内、耐火構造(RC造など)は25年以内
- 上記を超えている場合は「耐震基準適合証明書」が必要
- 登記上の床面積:40㎡以上
- 借入期間:10年以上
中古住宅の購入を検討している方は、物件の築年数だけでなく、証明書の有無や構造もチェックポイントとなります。
ポイント3:所得制限が引き下げに
以前までは「年収2,000万円以下」であれば控除対象でしたが、2025年からは「年収1,000万円以下」に制限が厳しくなっています(課税所得ではなく、給与収入ベース)。これにより、控除対象から外れる方も出てきており、購入前の収入確認が重要です。
控除額のシミュレーション【年収500万円/借入3,000万円】
住宅ローン控除の具体的な節税効果をシミュレーションしてみましょう。
- 借入金額:3,000万円
- 金利:1.5%(全期間固定)
- 返済期間:35年
- 年収:500万円
- 住宅:長期優良住宅(13年控除対象)
1年目の控除
- 年末残高:約2,940万円
- 控除額:2,940万円 × 0.7% = 約205,800円
累計控除(13年間)
- 年々残高は減るため控除額も減少
- 合計控除額はおよそ180万〜200万円程度
これは所得税・住民税の負担軽減につながり、ローン返済と家計のバランスを保つためにも非常に有効な支援です。

住宅ローン控除の落とし穴と注意点
制度を最大限に活用するためには、いくつかの「落とし穴」に注意する必要があります。
注意1:省エネ基準を満たさないと対象外
最近では、建築コスト削減のために仕様を簡略化した建物も見られますが、省エネ等級や性能証明書を取得していない場合、控除の対象から外れてしまいます。
→性能基準を満たすことを証明する書類(認定通知書・BELS評価書・適合証明書など)の取得が必要です。
注意2:申請漏れ・書類不備で控除が無効に
控除を受けるには、確定申告(もしくは年末調整)での手続きが必要です。特に初年度は、次のような書類が求められます。
- 住宅ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書・請負契約書
- 性能証明関係書類
書類の一部でも不備があると控除が受けられない可能性があるため、事前に税理士や不動産会社へ確認しておくのが安心です。
注意3:入居のタイミングも重要
控除を受けるためには、原則として「その年の12月31日時点で入居していること」が条件となっています。つまり、12月中旬以降の引き渡しや、入居が年明けにずれ込むと、1年目の控除が受けられなくなる可能性もあるのです。
→計画的に建築・引き渡しスケジュールを調整することが必要です。

AVANTIAのアドバイス:控除を最大限に活かすには「事前相談」が鍵
税制の制度をフルに活用するには、購入後ではなく“購入前”の準備が何より重要です。AVANTIAでは、以下のようなサポートを実施しています。
✔︎省エネ基準を満たす住宅の選定・設計サポート
✔︎控除対象の証明書取得スケジュールの管理
✔︎税理士・FPとの連携による控除シミュレーション
✔︎入居・登記のタイミング調整のアドバイス
控除の条件は年々細かくなっており、「自己判断で進めたら対象外だった」というケースも少なくありません。早めのご相談が安心と節税への第一歩です。
控除の“対象外”にならないために今からできること
- 物件選びの段階で「省エネ基準適合」かを確認
- 必要な書類を設計・施工段階から揃える計画を立てる
- 入居スケジュールをしっかり逆算
- 控除の有無によって、総支払額の試算をしておく
- 年度末(12月)を意識した資金・契約スケジュール管理
無料で受けられる控除シミュレーション、ご利用ください
AVANTIAでは、控除制度を踏まえた資金相談・税制活用アドバイスを無料で行っています。
「自分がどれくらい控除を受けられるか」
「建物の仕様が要件を満たすのか?」
「控除を前提にすると、どれくらいの予算で検討すべきか」
このようなお悩みに、実務経験豊富なスタッフが個別に対応いたします。
👉 控除対象の建物を見る
👉 税制・資金計画のご相談を予約
👉 控除額の試算ツール